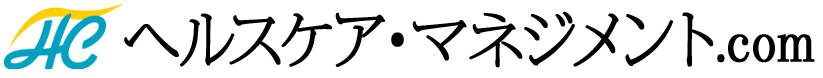DATAで読み解く今後の方向性 地域医療・介護向上委員会【特別編】
第71回
社会保障制度の
持続可能性を再考する⑦
2024年診療報酬改定はブラス改定で決着したが、財務省主導による医療費抑制政策は今後も進められていくのだろう。複数回にわたり、医療を含む社会保障制度の持続可能性について検討してみたい。
診療報酬は包括化すべきか
そのメリットとデメリット
2024年の診療報酬改定は最終的にはプラス改定に落ち着いたものの、財務省主導による医療費抑制は今後も進められていくだろう。今回から、給付の抑制の観点から、定量的な視点を交えて論じていく。
以前から、慢性疾患に関する診療報酬については、「包括化すべき」との意見があった。外来については「地域包括診療料」がその一例だ。しかし、広がってはおらず、現在、外来診療のほとんどが出来高の支払いとなっている。
医師にとっては、検査をしたり、薬を出したりするほど売上が上がる構造だ。出来高支払いだと、医師が予防医療を推進して、薬を出さずに済むようにすることへのインセンティブは働かない。これが、日本の外来受診回数が世界で2位(1位は韓国)の水準となっている要因ともいわれている。
たとえば、疾患ごとに診療報酬を包括化すれば、受診回数は減少し、医師がゆっくり診療にあたることができるというメリットも生まれる。その分、1回あたりの報酬は引き上げればよかろう。他方、診療報酬の包括化には、診療回数の不必要な減少や診療内容の簡素化等(検査を減らす等)の恐れがあるが、これには医療の質を低下させないように外部からのチェックが必要になるだろう。
入院医療では包括が進むが
支払い対象等の課題は多い
私はさらに踏み込んで、入院についても報酬の包括化を今以上に進めるべきだと考える。
日本では、DPC/PDPSという急性期病院の入院費用を包括払いにする制度が導入されているが、包括払いの対象は1日あたりで、諸外国のように1入院あたりにはなっていない。
そのため、諸外国に比べて、極めて長くなっている在院日数を短縮(在宅等への早期退院)しようというインセンティブが、病院経営に働かないといわれている。
回復期(リハビリ等)を含めた一連のエピソードベースの包括支払いも試みられている。そういった包括支払いを導入することで、給付抑制だけでなく、在院日数の短縮、ひいては医療の質の向上が期待される。
もっとも、最近は、DPC/PDPSの浸透や低侵襲医療の普及等により、全体的に急性期の患者の在院日数は短くなっており、集患力の低い急性期病院の病床稼働率は低下しつつある。
病床があるのに埋まっていないと、経営者はこれを埋めようとする。供給が需要を生み出してしまうのだ。このような状況を経済学的には「供給誘発需要」と呼んでいるが、病床を埋めることで、病院の経営は改善するが、医療費は増大し、医療の質は低下する可能性が高い。
精神科や慢性期の病院では、認知症の患者が増え、実質的に介護施設化しているところも多いと聞く。介護施設と医療必要度が変わらない入院患者の診療報酬は介護並みに引き下げていくことも検討すべきだろう。
在院日数の短縮(在宅への早期退院)やそれに伴う病床削減によって2兆円以上の大きな給付抑制効果があるとの試算がある。結構な額だ。
財務省は、地域別の診療報酬制度の導入や、それを通じて、医師不足地域の医師の給与水準の引き上げを検討している。
しかし、そのような社会主義的な取り組みには反対だ。診療報酬は、確かに政策誘導に大きな効果を発揮するが、調整を間違えることも多い。私はもっとマーケットメカニズムに任せるべきだと考える。給与水準の引き上げは、たとえば、混合診療の解禁によって、指名料のようなものを認めることでも可能である。
延命治療は必要か否か
費用対効果を検討すべき
給付の抑制の議論の際に避けて通れない、終末期医療についても取り上げる。
終末期をどのように定義するかは、個人の価値観によっても変わる。また、老化に伴って、人はさまざまな病気になる。極論を言えば、高齢者医療そのものが延命だという指摘も間違いではない。
私は、後期高齢者の医療保険は介護保険と統合し、一部の医療の保険適用除外を検討すべきではないかと考える。要介護になった場合の医療・介護サービスを包括的に提供できるような報酬体系をイメージしている。
延命治療をすべきではないというと、「お金がない人には死ね」と言っていると誤解する人が多いが、そうではない。
認知症患者数は1000万人、要介護者数は700万人を超えた。胃ろうをつくって、経管栄養を得ているほぼ意識のない人もたくさんいる。このような人たちがまだ元気だった時に、延命治療を受けたいと表明していたのかといった、いわゆるACPの推進が求められている。
現在、胃ろうを用いているとされる140万人にかかっている医療と介護の費用の合計は、1人あたり年間500万円とした場合、総額で年間2兆円がかかっていると試算できる。乱暴な試算だが、「食べられなくなったらあきらめる」という考えが主流となり、胃ろう造設者が激減した場合、医療・介護費用は2兆円以上減ることになる。これは一例だが、延命治療に多額の公費が使われていることがわかる。
少し前に、102歳の高齢男性に心臓手術を行ったことを称賛する記事をみた。治療に係る費用は500万円だが、高額療養費制度があり、本人の自己負担は2万4000円と少なく、残りの498万円は主に現役世代の負担だ。
その男性は2年後に亡くなったという。男性に使われた500万円は、2年間の延命に寄与したのか。それとも、余命が2年だったので、無駄な医療費だったのか。
費用対効果の評価を最も古くから制度的に導入したのが、英国のNICEという組織だ。医療サービスの費用対効果を評価すべく、QALY(質調整生存年)という単位を用いて、公費で賄うかどうかの推奨を行ってきた。
QALYの基準値は、2~3万ポンドといわれている。日本でも、2019年から費用対効果の制度が本格的に開始されたが、対象は一部の高額薬剤に留まっており、必ずしも年齢にフォーカスしたものではない。超高齢者に対する高額医療に関する診療ガイドラインを作成し、保険償還していく方向性が考えられる。
次回も引き続き、社会保障制度の現状と課題、今後の方向性を読み解いていく。(『CLINIC ばんぶう』2024年9月号)
筑波大学医学医療系客員准教授
いしかわ・まさとし●2005年、筑波大学医学専門学群、初期臨床研修を経て08年、KPMGヘルスケアジャパンに参画。12年、同社マネージャー。14年4月より国際医療福祉大学准教授、16年4月から18年3月まで厚生労働省勤務