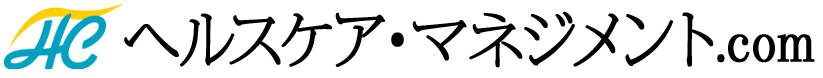デジタルヘルスの今と可能性
第40回
医療機関の「イノベーション」
今一度その可能性を考える
「デジタルヘルス」の動向を考えずに今後の地域医療は見通せない。本企画ではデジタルヘルスの今と今後の可能性を考える。今回は、「デジタルヘルスへ向けた準備段階」である今年から、2030年までに起こり得る医療界の変化について考える。
「イノベーション」の本来の意味とは?
本連載も、今月で40回目を迎える。前回は、「医療機関のあり方がここ数年で大きく変わっていく」「医師が増え、開業医も増えていく」「人々の生活スタイルもニューノーマルへと変わるなかで、他の医療機関との差別化を今こそ考えることが必要」――などの話をした。そんななか、私は最近、「イノベーション」について考えたり、こうして誰かに話をしたりする機会が増えている。
そこで、今回はこの「イノベーション」について説明するとともに、医療機関として今後どういうことができるのか、そのヒントを提示できればと考えている。
現在、一般のビジネス界隈では、次のようなことが言われている。「新型コロナウイルス感染症の流行により、今までの社会のルールが変わってきている。先行きが不確かななかで、企業は『イノベーション』を起こして、新たな時代を創造していく必要がある」
といったことだ。読者の皆様もよく聞く言葉だと思われるが、そもそも、「イノベーション」とは何か、改めて考えてみてはいかがだろうか。
「イノベーション」という言葉を調べてみると、「技術革新」と訳されている場合が多い。1956年の『経済白書』で「技術革新」と訳されたのを機に、ブームとなったようだ。しかし、果たして「イノベーション」は、純粋な「技術(テクノロジー)」に限ったものなのだろうか。
「イノベーション」への理解を深めるべく源流をたどっていくと、ヨーゼフ・シュンペーターという人物に行き着いた。
シュンペーターは、“イノベーションの父”と言われ、「イノベーション」を「新結合」という言葉で表現している。見てのとおり、ここには「技術」や「革新」はどこにもなく、新しい結合といった意味合いだけである。
また、同時にシュンペーターは、この「イノベーション(新結合)は『発明』とは区別される」ということ、そして、「新しいものを創るといった意味だけでない」という話もしている。新しいものを創るというのはその一部分であって、その他も合わせくでこの内容が含まれるとされている。
①新しい生産物の創出
②新しい生産方法の導入
③新しい市場の開拓
④新しい資源の獲得
⑤新しい組織の実現
差別化の価値は患者・消費者が決める
そして、この「イノベーション」の達成には、「考える過程」「実行する過程」の、大きく2つの過程があるのではないかと考えられる。
前者は、医療機関でいうと、「どのような患者さんを対象にして、どのような患者さんから役に立って(価値があって)新しいと思われることを考えるか」ということだ。ここで大切なのが、既存の考え方で「イノベーション」を考えていくと「改良になりがち」ということだ。他業種の例を挙げると、今まで日本企業はリモコンをよりよいものにしようとするときに、品質の向上を考え、改良することで、さまざまなボタンの増えたりモコンをつくってきた。
医療機器に関しても、できることが増え、精度が向上した医療機器へ改良してきた。ただ、もちろん医師が自分の診療の質を上げることは重要だが、その質の向上を患者さんは理解できるだろうか。研修を終え医師3年目で開業した院長の診療所に患者さんが通院するのは、診療レベルの差よりも、その他のアクセス上の利便性だったり、診療時間が柔軟で深夜までやっていたり、土日もやっていたりといった通いやすさに起因するもので、そのほうが差別化としてわかりやすく、満足度につながるため、まだ若く診療のレベルもそこそこの医師のもとにも、患者さんが通院したりするのだ。
この診療所の価値というのは、お金を払う患者さんが決めることであるということを割り切る必要がある。だからといって、臨床レベルが低いままで開業するスタイルが正しいというわけではない。そこは医師の倫理感の問題だ。患者さんが自分を医師として頼ってくれたときに、充分足るスキルを持っているか、それを担保するかどうかは、医師の倫理観にかかっている。
閑話休題。先ほどのリモコンの例に戻ろう。もし、電気屋で多機能なリモコンを見て、「こんなに機能がついてなくても、最低限の機能のあるリモコンと変わらないよ」と思う消費者がいるとすれば、もしかすると、医療機関を選ぶときも「医師でありさえすればいい」と思っているのかもしれない。
ここで言いたいのは、差別化としての価値は対象者が決めるものであるということだ。
それを前提に考えると、ほかにも医療機関のさまざまな活用が見えてくるかもしれない。元来医療機関は、病気やけがを患った人を対象に診察・治療するための場所であると考えられている。だが、対象者を企業に変えてみると、「企業が新しい商品やサービスを立ち上げる際に、そのもととなる知見・アイデアをもらいに行く場所」と捉えることもできるだろう。
実際に、現在は大学病院の教授などが製薬企業の顧問やアドバイザーとなっているケースが多いが、患者にとって一番身近にある診療所の知見から、企業へ開発のアイデアを提供したり、企業と共同開発したりもできるだろうし、保険診療事業以外の療所の副収入にもなり得るかもしれない。これは、先ほどのシュンペーターの5カ条でいうと、「③新しい市場の開拓」に該当するだろう。
これからの医療機関は、「診療をする場所」以外にもさまざまな活用の可能性があると考えている。デジタル機器の導入といったツールの話に限らず、医療機関における「イノベーション」をぜひ考えてみてほしいと思っています。(『CLINIC ばんぶう』2021年4月号)
(京都府立医科大学眼科学教室/東京医科歯科大臨床准教授/デジタルハリウッド大学大学院客員教授/千葉大学客員准教授)
かとう・ひろあき●2007年浜松医科大学卒業。眼科専門医として眼科診療に従事し、16年、厚生労働省入省。退官後は、デジタルハリウッド大学大学院客員教授を務めつつ、AI医療機器開発のアイリス株式会社取締役副社長CSOや企業の顧問、厚労省医療ベンチャー支援アドバイザー、千葉大学客員准教授、東京医科歯科大臨床准教授などを務める。著書は『医療4.0』(日経BP社)など40冊以上