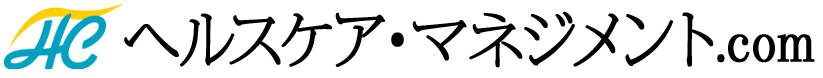お世話するココロ
第150回
医師との思い出
これまで看護師として働いてきた35年の間に、たくさんの医師と出会いました。昨年から再び病棟勤務となり、改めて、当時の思い出がよみがえってきます。
科によって違った医師の気質
昨年から病棟勤務となり、職場に医師の姿を見るようになりました。それまで働いた訪問看護室では、医師とのやり取りは主に電話や電子カルテ。連携は密だったものの、職場に医師の姿はなかったのです。
私の看護師としてのスタートは、1987年4月に東京厚生年金病院(現 JCHO東京新宿メディカルセンター)の内科に入職した時から始まります。
これまでを思い返せば、私は医師との関係に恵まれていました。いまだ看護師は医師の助手と考えるような人もいるなか、看護師の声にきちんと耳を傾ける医師と働いてきたからです。
これは私が働いてきた領域にもよるものかもしれません。はっきり言えば、内科、精神科、緩和ケアはいずれも医師の力だけではすっきり治せない病気を扱います。
進行がん然り、糖尿病や高血圧然り……。うつ病や統合失調症なども、長く病気と付き合う傾向にある、いわゆる慢性病です。
慢性病では、医師の診療と同じくらい、生活指導や身体的・精神的なケアなど、看護師の力が不可欠と言えます。
逆なのが、手術を行う外科系です。ここでは、「俺の技術で治すのだ」と血気盛んな医師が多く、多少横暴でも周囲は受け入れる傾向があったように思います。
数年経ったある日、手術室で働く先輩看護師からこんな話を聞きました。
「外科のA先生は普段はまあまあ穏やかだけど、手術になると、ものすごく神経質。介助についた看護師のメスの渡し方が気に入らないと、投げて返してくるから、危なくてしょうがない」
A医師は、大声で看護師を怒鳴る医師が多い当時の外科のなかで、とても紳士的な人でしたが、手術時は違ったのです。
こうした診療科ごとの医師の気質は、今はどうなっているのでしょう。当時に比べれば、人間的な配慮ができる人が増えたとは思うのですが……。
蛇足ながら、眼科、耳鼻科などの小外科は一つのことを極めるマニアックな人が多く、整形外科は自らもスポーツが好きな人が多かった印象があります。
とはいえ、医師がその診療科を選ぶ動機もさまざまあって、親の代から医師で診療所や病院があれば、選ぶ余地はありません。自ら選んだ診療科かどうかも、その診療科らしいキャラクターかどうかが背景にありそうです。
精神科医という人たち
私が精神科以外の科で働いたのは、入職してすぐ勤務した内科病棟での9年間と、看護師長として精神科病棟と兼務した緩和ケア病棟で、訪問看護を含め、精神科医と26年間かかわっています。
精神科医の特徴を言語化するのは簡単ではありません。ただ、常々思うのは、精神科医は自分の診療スタイルをとても大事にしているということです。
たとえば、ある医師(B先生)は、患者さんとの面談日をあらかじめ決めておき、それ以外の日は希望があっても、応じませんでした。私はそのやり方に、強い反感を抱いたものです。なんで融通を効かせないのか。不思議でなりませんでした。
付き合いの長いC医師に気持ちを話すと、「宮子さんや、ほかの看護師の皆さんがそう思うのももっともだと思う」と受け止めてくれたうえで、次のように話しました。
「ただ、扱う病気もあるんだと思います。B先生は、人を攻撃するような人格的に難しい患者さんをたくさん診てるんですよね。だから、面談の枠を明確に設定するんだと思う」
確かに、B医師が受け持つ患者さんは、かかわりが難しい人ばかりでした。うつ病、統合失調症などと明確な病名もつかず、薬がすっきり効きません。
この場合、医師との約束が設定された枠での面談になります。これをしっかり守ってもらう、それ自体が治療であり、ただ患者さんの言うなりになってはいけないのです。
C医師の説明で、B医師の診療スタイルが、受け持っている患者さんの特質からも必要なのだと理解できました。
一方、C医師はと言えば、C医師を慕って来る、素直な患者さんがたくさんいるのが特徴でした。B医師が予定を立てて長く時間をとって面談するのに対し、C医師の面談は短め。時には数分で終わり。ただし、希望すればいつでも面談に応じ、いずれの患者さんも、おおむね満足していたようです。
精神科医は、患者さんのキャラクターや病気について、得手不得手があるように見えます。己を知り、苦手な患者さんは、それが得意な医師にまわす。これもまた、大事なテクニックとみえるのです。
これは患者さんにも言えること。精神科医と患者さんの間には、どうしても相性があります。かかった精神科医と合わないと感じたら、転医に遠慮は不要と声を大にして言いたいところです。
宝物のような11年
そして、看護師と医師にもまた、相性があります。私が東京厚生年金病院(当時)の精神科病棟でともに働いた医師たちは、本当にいい人たちで、苦楽をともにした実感が今も残っています。
私が退職するより前に、精神科部長だった男性医師が定年退職し、ほかの医師もほとんどが入れ替わりました。この時の11年は、私にとって、宝物のような年月です。
部長は医師として働く傍ら哲学研究のグループに参加していて、学びながら実践を続ける私にとって、手本になるような存在でした。
人生をひどくこじらせた、難しい年配の患者さんとのかかわりに秀でており、吟味された言葉で、患者さんに接していました。
半面、診療以外ではアパウトすぎる点もあり、管理者同士として言い合いになったこともあります。それでも、本当に大きな問題が起きた時は、ともに協力し合える関係ができていました。
ある看護師が、その部長を評した、「信用できないけど、信頼できる人」という言葉は、まさに適切でした。ちょっとした間違いや不正確さがあり、診療以外の事務作業などは信用しきれないが、一度問題が起きれば決して逃げない。信頼できる人だったのです。
信用も信頼もできる人ならいいわけですが、何事も完璧な人なんていません。私にとっては、「信用できるけど、信頼できない人」よりも、格段にいいと思いました。
精神科部長との思い出はたくさんありますが、長く診てきた患者さんが自死した時のことが忘れられません。その患者さんは入院中に無断外出をして自死したため、私も部長も責任を痛感しつつ、忠者さんが運ばれた病院に向かいました。
ご遺族は、私たちと長年の信頼関係があり、突発的な状況を受け入れ、労いの言葉さえかけてくれたのです。
帰りのタクシーの車内で交わした部長との会話が、今も耳に残っています。
「もう、気持ちを決めていたのでしょうか。いつからなのか……。気持ちを決めた人を止めるのは本当に難しいですね。残念です」と言うと、部長はこう答えました。
「そうですね。自死する人は、僕たちが思うよりも少しだけ、絶望が深いのでしょう。それに気づかなければいけないのだけれど、なかなか気づけませんね」
それを聞いた時、自ら死を選ぶ患者さんの絶望の深さを思い、本当に胸が苦しくなりました。その深い絶望に、少しでも思い至れる看護師でありたい。
その気持ちを、これからも持ち続けたいと思います。(『ヘルスケア・レストラン』2023年3月号)
みやこ・あずさ●1987年、東京厚生年金看護専門学校卒業後、2009年3月まで看護師としてさまざまな診療科に勤務。13年、東京女子医科大学大学院博士後期課程修了。博士(看護学)。精神科病院の訪問看護室勤務(非常勤)を経て、同院の慢性期病棟に異動。長年、医療系雑誌などに小説やエッセイを執筆。講演活動も行う。看護師が楽しみながら仕事を続けていける環境づくりに取り組んでいる。近著に『まとめないACP 整わない現場、予測しきれない死』(医学書院)がある