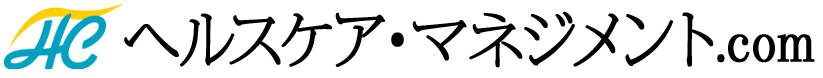“その人らしさ”を支える特養でのケア
第45回
見極めが難しい認知症の終末期
管理栄養士が担う終末期ケアとは
認知症のご利用者を多くみている当施設では、軽度から重度までさまざまな方の栄養管理を行っています。なかでも終末期ケアを要するご利用者には、栄養ケアの仕方や食事提供に対して慎重になります。今号では実際に認知症の終末期ケアで携わったAさんの事例について、紹介していきます。
栄養評価で予測できる?認知症の終末期
先月号で、重度認知症の栄養ケアについて紹介しました。認知症が重度になるまでの期間は個人差が大きく、予測できません。ですが個人的な経験から、食事介助が必要で意思の疎通がまったくできない状態であっても、必要栄養量を十分に摂取できている方は、安定している期間が長いように感じます。
さて、今回は認知症の終末期についてお伝えします。重度認知症の時と同様に、認知症の終末期についてはさまざまな定義がありますが、主に「一人で移動できない、意味のある会話ができない、ADLが全介助、老年症候群(誤嚥性肺炎、腎盂腎炎、菌血症、褥瘡、繰り返す発熱、著しい体重減少など)」の合併と解釈することができます。なかでも全米ホスピス緩和ケア協会(National Hospice and Palliative Care Organization)の認知症の臨床的予後決定因子には「庶下障害や拒食が原因で『6ヵ月間に10%以上の体重減少』と『血清アルブミンが2.5g/dl以下』であり経管栄養や静脈栄養を選択しないことで水分とエネルギー摂取が絶たれ生命維持に影響している(要約)」と具体的に提示されています。このことから、管理栄養士が栄養評価で注目する項目にも、認知症の終末期を予測するためのヒントがあることがわかります。
2020年11月号の本誌で「重度認知症のご利用者で嚥下障害のため食事が食べられない方」の事例を紹介しました。経過を振り返ると、このご利用者は教科書的な認知症の終末期であったと思います。
嚥下機能と食事の様子で終末期ケアを検討する
認知症の終末期ケア、と意識して取り組んだことはありませんが、ほとんどの方が認知症を発症している特養では、看取りケアの多くが認知症の終末期ケアといえます。これまでの経験では医療的なかかわりより、ご本人の苦痛を軽減することに重きを置いた緩和的なケアであると感じています。実際、多職種でのカンファレンスにおいても「ご利用者が安楽か」「よいと思ったケアが苦痛を与えていないか」を前提に話し合いが行われています。
栄養ケアに注目すると、嚥下機能に見合った食形態であることはもちろんですが、「お好きだった物の提供」や「ムセが頻回なら少量の摂取でも中止する」など、ご本人への配慮が多くなります。この時ばかりは必要栄養量や栄養バランスは横に置いておいて「また食べられるようになったら栄養が十分か検討すればいい」と考え、対応しています。
「医療と看護の質を向上させる認知症ステージアプローチ入門 早期診断、BPSDの対応から緩和ケアまで」1)を読み込むと、認知の終末期は「下機能が消失しているかどうか」がポイントのようです。嚥下機能の消失については客観的な評価が必要と書かれており、当施設では頸部聴診(訓練中の私がたどたどしく担当しております)と食事中の様子を総合的に勘案し、評価しています。
食事中の様子を観察し、嚥下の確認が困難なこと、口腔内に食物が長く残ること、ムセや咳払いが頻回であること、経口摂取開始後から痰絡み音(ゴロゴロ音)があること、頻回な傾眠で食事時間が取れないこと、などが確認されると多職種で今後の食事対応の検討を行い、ご利用者の苦痛のない状態を保つために何ができるかを考えています。
苦痛のない栄養ケアで安楽な最期を支える
当施設で認知症の終末期ケアを行ったAさんの事例を紹介します。Aさんは認知症で入居された方です。入居当時は杖歩行ができ、いつもニコニコと朗らかな方でしたが、認知症の進行からADLが低下し、生活全般に介助が必要になりました。
意思の疎通も難しくなり、食事も全介助。嚥下障害も発症したため、嚥下調整食や経口補助食品を提供することで、栄養量の確保ができていました。このような状態で約2年間、穏やかに過ごしていたAさんですが、徐々に嚥下後に口腔内の残留が目立つようになってきました。
この頃から食事中も傾眠となってしまうことが増え始め、一度に食べられる量が減ってきたため必要栄養量の確保が難しくなってきました。嚥下機能の低下を目の当たりにしながらも、看取りケアに移行していたこともあり、食べやすい物を食べられるタイミングで提供していましたが、食事摂取量の低下が顕著です。
打つ手がないまま、ついにAさんは飲み込むことができなくなりました。頸部聴診を行っても嚥下音が聞こえることはまれで、嚥下してもすぐにむせてしまうことばかりになりました。このタイミングで行ったカンファレンスでは、嚥下機能の低下が著しく食べることがご本人の苦痛になることから「食事提供の中止」が選択され、しっかり覚醒している時にのみ、少量の経口摂取を行うこととなりました。
ミールラウンドでは覚醒状態の確認や食前に痰絡みがないか、経口摂取時の姿勢は適正かを確認しながら少量のゼリーを提供します。それでも一口食べられればいいほうでした。
しばらくしてAさんは亡くなられました。窒息や誤嚥性肺炎を発症することなく、穏やかな看取りとなりました。
Aさんの事例では、毎食の食事提供の中止の判断が重要だったかと思います。嚥下障害が進行していると情報共有した時点で、食事を中止する目安ができていました。本事例については、口腔内に食物残留が多く、長時間停滞している時やムセの頻度が高い時、覚醒が保てない時に食事を中止していました。
徐々に嚥下機能が低下していく経過で、介護者側としては「何とか食べてもらいたい」という気持ちが強くなってしまうのは仕方がないことだと思います。しかし、認知症の終末期の緩和ケアだと考えると、ご本人の安楽が最優先となります。食事をとることが苦痛になるラインを見極め、食べられる範囲で栄養補給してもらうことに一役買えたのではないか、と思っています。
認知症の終末期ケアでは、嚥下機能の低下と苦痛緩和の目的でしばしば食事を出さない事例を経験します。「食べていないことでミールラウンドを行えないのでは?」と思う方もいらっしゃると思いますが、食べられたかどうか、ご様子はどうか、食事以外にどんなケアが行われているか、管理栄養士も確認したほうがよいことはたくさんあります。ご利用者の最期にかかわることで、新たに見えてくることも多くあり、今後も積極的にかかわっていきたいと思っています。(『ヘルスケア・レストラン』2021年9月号)
参考文献
1)平原佐斗司著:医療と看護の質を向上させる認知症ステージアプローチ入門
早期診断、BPSDの対応から緩和ケアまで.中央法規出版、2013
特別養護老人ホーム ブナの里
よこやま・なつよ
1999年、北里大学保健衛生専門学校臨床栄養科を卒業。その後、長野市民病院臨床栄養研修生として宮澤靖先生に師事。2000年、JA茨城厚生連茨城西南医療センター病院に入職。同院の栄養サポートチームの設立と同時にチームへ参画。管理栄養士免許取得。08年、JA茨城厚生連茨城西南医療センター病院を退職し、社会福祉法人妙心福祉会特別養護老人ホームブナの里開設準備室へ入職。09年、社会福祉法人妙心福祉会特別養護老人ホームブナの里へ入職し、現在に至る