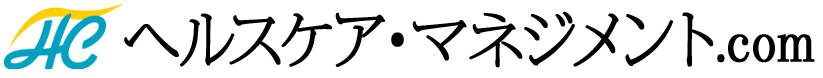お世話するココロ
第122回
夜間の巡視で
看護学生さんと話をした時、「夜の病棟は怖くないか」と聞かれました。看護師になりたての頃は、夜勤に入ると、幽霊が出ないかおびえたものです。ところがある事件に遭遇してから、幽霊が怖くなくなりました。なぜなら、生きた人間のほうが怖いと思うようになったからです。
人の死には慣れない
私が看護師になって初めて働いたのは、内科病棟です。重症の患者さんも多く、多い時には年間50人近くが亡くなりました。入院待ちの患者さんがいれば、空いたベッドには、すぐに次の患者さんが入ります。
亡くなった患者さんの印象は強く、多くの方が記憶に残っています。一方で、看取りは1つの業務でもあって、淡々と業務に当たる部分があるのも事実です。
ある日の夜勤では、夜勤のはじめに亡くなった患者さんを病院からお見送りしたあと、夜中その個室に急患を受けました。しかしその方も明け方に亡くなり、夜また出勤すると(当時の夜勤は2日続きでした)、そこには日勤で別の患者さんが入院していたのです。
確か、働き始めて2年目の頃の話で、私はもう、夜勤の業務を行うのに必死でした。人が日常的に亡くなる環境は、今振り返ると尋常でないわけですが、当時はそこでベストを尽くそうと、受け入れていたように思います。
人手が足りない時は、亡くなったあとの患者さんの身体を、1人で拭いたこともあります。時間が経つと、あっという間に冷たくなる身体に、「ああ、血が通わなくなると、人間はどんどん冷たくなるのだな」と驚きました。
今思えば、怖がりの私がよく亡くなった方と1人でいたものです。思うに、さっきまで生きていた人という感覚が強く、死者という実感が薄かったのでしょう。
これは、前回お話しした、居宅死を見つけた時の感覚とは大きく異なります。家は生きる人が生活する場。それに対して当時の内科病棟は、生と死が混在する場だったのだと思います。
ちなみに、あまりにも日常的に人が亡くなるので、それに慣れたら怖いな、と思ったことがありました。しかし、これは私の場合杞憂だったといえます。いかにたくさん人の死を見ても、常に死は特別なもの、神聖なものであり続けました。
1つには、きちんとした職場環境がよかったのかもしれません。けれども、そもそも死というのは、慣れようのない力をもった事象なのではないか。そんな気もするのです。
真夜中の巡視
内科病棟でようやく仕事に慣れた頃、夜間の巡視が怖くなりました。夜勤では、患者さんの生存確認の意味でも、1時間に1回の巡視が求められます。その際は、空いている個室やベッドも見なければなりません。
ある日の巡視で、長く入院していた患者さんが亡くなったあとのベッドを見た時、私は不思議な感覚を覚えました。それは、亡くなった患者さんの気配といえばいいのでしょうか。
霊感のある人なら、何か見えていたのかもしれません。それを思えば、気配だけで本当によかった……。ほどなくそのベッドには別の患者さんが入り、気配は消えました。
改めて書いてみれば、これだけの話です。それでも怖がりな私は、以後しばらく夜間の巡視が怖くなってしまいました。
そしてそんなある日のこと。この恐怖を吹き飛ばすような事件が起こりました。
心不全で個室に入院していた90代の女性が、なんと自分のふくらはぎを、自分の指ではぎ取ってしまったのです。この時の光景は30年近く経った今も忘れられません。
その日の夜勤のはじめ、22時前にまわった時、女性は私に「足の湿布をはがして」と話しかけてきました。希望に添おうとして近づいて布団をまくると、足に湿布は貼られていません。その旨を告げると女性は「ああそうだったのね。ありがとう」と、眠そうに答えました。
異変が起きたのは、明け方です。その部屋に入った別の女性看護師が、声にならない声を上げ、廊下に走り出てきました。「異常行動で、大変なことになっているのよ!当直医を呼ぶ!」。
私が入れ替わりに病室に入ると、目の前の光景はまさに地獄絵図でした。
ベッドに足を投げ出して座っている女性は、冷や汗をかきながら、なんと、ふくらはぎの肉を自分ではいでいたのです。
血まみれの手で汗を拭いていたので、首筋や顔まで血まみれになっていました。
「いったいどうしたんですか!」と叫んだ私に、女性は「湿布……やっとはがれたわ」と、にやりと笑ったのです。私は恐怖のあまり気を失いそうになりました。
異常行動の怖さ
そのあとは当直医や当直の看護師長が駆けつけ、皆、異常行動のすごさに絶句。少しずつ冷静になった私たち看護師は、混乱した様子の女性をなだめながら血まみれの身体を拭き、ベッドに横たえ、傷口の処置を医師に委ねました。
処置前、女性は軽い鎮静剤を注射され、穏やかに眠りました。軽い認知症はあったものの、異常行動はまったく予想外の出来事といえました。
幸いこの日の当直医は、ベテランの男性形成外科医でした。難しい傷口の処置に最も適した医師であり、実際、傷口はきれいになったのです。
しかし残念なことに、この日を境に、心不全はがくんと悪化していきました。終日酸素吸入が必要になり、動くとすぐに息切れがします。寝返りを打つのもつらそうで、急速に寝たきりの状態になっていったのです。
結局事件から10日ほど経って、女性は亡くなりました。傷口からの感染もあり、それも負荷になった可能性があります。
予想外の行動だったとはいえ、何か察知できなかったものかと反省も残りました。
とりわけ私が悔やんだのは、最初の巡視の際に言われた、「足の湿布をはがして」という言葉です。実際貼られていない湿布が、貼られているように感じたのは、むくんだ足のせいだったように思えます。
むくみのある足の違和感を湿布だと思い込んだ女性が、それをはがそうとしてふくらはぎの肉をはいだのではないか。そう思うとやりきれない気持ちになります。
そうであれば、むくんだ足を揉むなどの援助をすれば、足が楽になったかもしれません。そうすれば、肉をはがずに済んだのではないでしょうか。
このような反省をする一方、当時の光景を思い出すと、私はしみじみ恐怖にとらわれました。人間は、ひとたび思考が変調し、強い思い込みに駆られると、痛みも感じなくなるのですね。
駆けつけた時、「湿布……やっとはがれたわ」と言ってにやりと笑った女性の顔が、私はどうしても忘れられません。その瞬間私は、心底人間が怖いと思いました。
これ以降、私は患者さんが現実とは違うことを言っている時、以前より注意深く対応するようになりました。少なくとも、患者さんにとっては、それが現実なのかもしれないからです。
そしてもう1つの大きな変化は、亡くなった人よりも、生きている人のほうがはるかに怖くなったことです。そのおかげといっていいのかわかりませんが、霊的なものへの恐怖は遠ざかり、夜間の巡視も怖くなくなりました。(『ヘルスケア・レストラン』2020年11月号)
みやこ・あずさ●1987年、東京厚生年金看護専門学校卒業後、2009年3月まで看護師としてさまざまな診療科に勤務。13年、東京女子医科大学大学院博士後期課程修了。博士(看護学)。現在は精神科病院の訪問看護室に勤務(非常勤)。長年、医療系雑誌などに小説やエッセイを執筆。講演活動も行う。看護師が楽しみながら仕事を続けていける環境づくりに取り組んでいる。近著に「宮子式シンプル思考 主任看護師の役割・判断・行動力」(日総研出版)がある