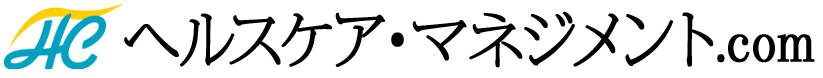デジタルヘルスの今と可能性
第68回
現行の医療提供体制から
これからの医療はどう変わるか
「デジタルヘルス」の動向を考えずに今後の地域医療は見通せない。本企画ではデジタルヘルスの今と今後の可能性を考える。今回は、日本における今後の医療の方向性について、デジタルヘルスも交えて改めて考えていく。
国民皆保険制度の成立時と現在では年齢分布が異なる
今回は、今後の医療の方向性について、私が考えていることを話していこうと思う。
現在の医療、特に日本において保険診療として行われている医療は、「病気」を対象としたものだ。そのため医師は、医学部の大学生のときに病気や症状、検査、治療を学んできた。
「病気」を対象にしたものというのは、患者に何らかの症状が出て、医療機関へ行って(オンライン診療も含めて医療機関と連絡を取って)、初めて医療がスタートするものである。しかし、この医療の形が今後大きく変わっていくと考えている。
まず一つは、現在の日本の保健医療制度だ。今の日本の保健医療制度は1960年代にスタートしている。負担の割合は時代ごとに代わってきているが、医療機関を受診したときに患者は7割引きないしは9割引きで医療を受けることができる。
労働世代が高齢者を支えているようになっているシステムだが、もともとこの皆保険制度が成立した1960年代あたりは、平均寿命が男性は65.32歳、女性は70.19歳だった。
これが2020年には男性81.46歳、女性87.74歳と、この60年間で男女ともに約15歳以上長寿になっているというわけだ。
若い労働世代が高齢の方を支えるようにできている皆保険制度のシステムは、当初と年齢分布が大きく変わってきてしまっているのだ。そのため、高齢者が増えて医療費が増大、そして労働世代が負担大となっている。
2020年代からの「医療4.0」の立ち位置
このような流れから、昨年出版した自著『医療4.0実践編』(日経BP社)では、次のように日本の医療の変化を20年ごとの分類で提唱している。
■1960年代に国民皆保険制度が実現し今の医療提供体制の礎ができた「医療1.0」
■高齢化が懸念されはじめ、老人保健法やゴールドブランが策定など今につながる介護施策が進んだ1980年代の「医療2.0」
■2000年代のインターネットの広がりとともに、電子カルテをはじめとした医療のICT化が進んだ昨今の「医療3.0」
そして、2020年代からの第4次産業革命に関連したテクノロジーを活用した新しい医療の形を「医療4.0」と提唱した。
この医療の変化は、プロダクトライフサイクルにおける「導入期→成長期→成熟期→衰退期」に当てはまっているのではないかと言及している。
つまり、20年からの「医療4.0」の時期は、過去の「医療1.0」からの一連のままだと衰退期にあたる。そのために、新しい医療の形、「シン医療」ともいえるものを実行していき、新しい成長サイクルを始めるべきと書かせていただいた。
これからの医療は「健康医学」が主流になる?
前書きが長くなってしまったが、本稿でこれからの医療として「私が「シン医療」と呼ぶ医療の形を考えたので、共有していく。
もちろん、「医療のデジタル化や遠隔医療が進む」というのは事実ではあるが、デジタルの利活用やどこでも医療を受けられるといったトピックスは、医療に対する「手段」のことを話しているだけで、今後の医療がどういうふうに認識されるのかという議論ではない。
私としては、今後の医療は「健康医学」に進んでいくと考えている。「健康医学」というのは勝手に自分が言い出している言葉だが、「健康→不調→病気→予後」という体調の変化のなかで、健康に対してエビデンスをもとに取り組むことを指している。
前述のとおり、医療はもともと「病気」を対象にしているものが多いです。医師の仕事としても最近、女性の健康などで「不調」をターゲットとしたり、リハビリなどで病気の「予後」に対してアプローチをしたりする取り組みも増えてきている。
イメージで表すと、医師が行う医療の対象領域は「不調←病気→予後」みたいな感じで、病気を対象としていた形から、前後の不調や予後の領域に拡大してきているように思える。
ただ、ここでは「本当はこうなったらいい」という理想の話をしよう。誰にも言わないが、「病気になる人が、この世から誰もいなくなるのが一番良い」はずだ。
今の医療で、なぜそれを言わないのかというと、もちろん、「病気になる人が誰もいなくなる」のは事実上困難だと思っている前提もあるし、今の医療制度の前提でいると、医療機関は患者がいなくなって立ち行かなくなるからだ。
このように、「病気になる人が、この世から誰もいなくなるのが一番良い」と純粋に考えると、そうなればいい社会があるはずだが、そのように考えてきていなかったように感じている。
私はここに、大きな概念の変革、次の医療の概念のヒントがあると考えていた。現在、自分は世の中が「病気や不調にならない社会」になったらいいと思っているし、「医師の(従来の)仕事がなくなる」と言われるかもしれないが、病気になって病院に行くということをなくすような変革を起こしたいと思っている。
そもそも病気になって病院に行くというのは、仮に法律の世界なら、「訴訟をされてから弁護士を探す」と同じようなものではないだろうか。
病気になったり、調子が悪くなったりして病院に行くということが主流である現在、これは訴えられたり、訴えられそうになって困っている人がたくさんいて、弁護士を探して相談している状態と同じように、私としては見えてしまっている。
もちろん言うまでもなく、法律の世界では今はこのように訴えられてから対応ではなく、「訴訟とならないようにする」ために、企業などは弁護士の先生を顧問や社内で雇用することで防ぐ対応をしている。医療もこれからは法律の世界と同じように、訴えられない(病気にならない)ことを目指していくようになっていくのではないだろうか。
そしてこの価値観の変化により、医師の仕事も病気を治すことから「健康増進」が中心となると考えている。(『CLINIC ばんぶう』2023年8月号)
(京都府立医科大学眼科学教室・デジタルハリウッド大学大学院客員教授/東京医科歯科大臨床教授/THIRD CLINIC GINZA共同経営者)
かとう・ひろあき●2007年浜松医科大学卒業。眼科専門医として眼科診療に従事し、16年、厚生労働省入省。退官後は、デジタルハリウッド大学大学院客員教授を務めつつ、AI医療機器開発のアイリス株式会社取締役副社長CSOや企業の顧問、厚労省医療ベンチャー支援アドバイザー、千葉大学客員准教授、東京医科歯科大臨床准教授などを務める。著書は『医療4.0』(日経BP社)など40冊以上