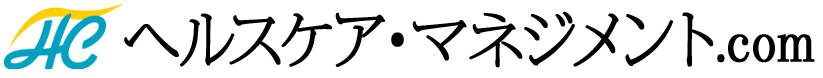お世話するココロ
第145回
「かわいそう」という気持ちの変化
病院には、病気や加齢でさまざまな不自由や苦痛に見舞われている人がいます。そのような人をお世話しながら、しばしば湧き上がる「かわいそう」という感情について、改めて考えてみました。
変わっていく患者さんへの気持ち
23歳で看護師になり、いつの間にか59歳。ふと自分の内面変化に気づくことがあります。
精神科病院の慢性期病棟では、何十年も精神疾患を抱えている患者さんが珍しくありません。10代後半で発病し、入退院を繰り返してきた50代の人の場合、病歴は40年を超えています。
多くの患者さんは、強い嘆きを表出させずに、淡々と生活しているように見えます。長い経過のな自らの状況を受け入れているのか。あるいは、感情の動き自体が失われているのか……。正直なところ、よくわかりません。
統合失調症の慢性期では、感情鈍麻(または感情の平板化)という症状が見られます。感情の抑揚が失われた結果、いきいきした印象がなくなってしまうのです。
こうした患者さんが多いなかで、40代までバリバリ働いていたという70代の女性が、最近よく話しかけてきます。彼女は、昔を思うと今の自分に価値がないように感じる、と言い、「もう年だから40代の頃みたいに、とは言いません。でも、こんなにも何もできなくなるなんて。やっぱりあんまりだわ」と嘆くのです。
私はしっかりと自分の年齢的な限界を理解したうえで、それでも諦められない部分について嘆く、彼女の気持ちは十分に理解できました。
「それはかわいそうに。おつらいですね。元気だった方ほど、そうでなくなった時に、絶望的な気持ちになりやすいようです。今は低調な時だから、何もせず休んでいていいのですよ。焦らずに過ごしましょう」
私の言葉に、涙ぐんで手を握ってくる彼女を見ていると、本当にかわいそうでなりませんでした。若い頃に発病して、仕事ができなかった人もかわいそう。そして、彼女のように、過去の仕事ぶりが忘れられない人もかわいそう。
病気になるというのは、本当に大変なことだと思います。
患者さんを対等に見るつらさ
30代半ばまで、私は患者さんに対して「かわいそう」という感情をもつことに、強い抵抗感がありました。それは、「かわいそう」という言葉に、相手を見下すようなニュアンスを感じていたからです。
患者さんは大人。決して見下すような態度をとってはならない……。これは私が看護学生の頃から、折に触れて自らを戒めてきたことでした。
ましてや、若いうちは自分より年上の患者さんばかり。こうした気持ちはますます強まっていったのでした。
また、看護は知識と技術が何より大切な専門職なのだ、という自負も患者さんへの同情的な感情を排除する傾向になりました。
通っていた看護専門学校には厳しい教員がいて、「やさしいだけの看護婦(当時)ではだめ。専門性の高い技術と知識があってこその看護婦」とはっきりおっしゃっていたのです。
なにぶん、40年近く前の話ですから、当時は多くの看護学校で似たような教育が行われていたことでしょう。
一方で、私のこうした感情は、時に患者さんを許せない、という怒りにもつながりました。
なぜなら、あくまでも患者さんと看護師は対等。同情的な感情を抱かないのであれば、看護師が患者さんに求めるものも出てくるかです。
たとえば、患者さんから暴言を吐かれたりすると、「対等な人間として許せない」という感情が湧いたものです。しかし、相手が終末期の患者さんや理性的な抑制を期待できない認知症の人だったりすると、そうそう反論はできません。
いや、当時だって、状況によっては自分のつらい気持ちを患者さんに伝えてもいいと思っていました。しかし、わだかまりが残ったまま看取るつらさを経験してからは、何も言えなくなってしまったのです。
患者さんを対等に見るからこそ感じてしまうそのつらさは、かなり長い間、私の大きなテーマになっていました。
やはり患者さんはかわいそう
こうしたつらさを抱えつつ、私は看護師を続け、自分の感情についていろいろ考えてきました。そして40代になった頃から、「病気になる人はかわいそう」と思うことに葛藤がなくなったのです。
このように変化した一番の理由は、私自身の加齢でしょう。加齢は、多かれ少なかれ、私たちからエネルギーを奪います。私は、自分の感情にこだわる根気が薄れたと自覚しました。
今思うと、患者さんをかわいそうと思ってはいけないと、なぜあんなに固執したのでしょうか。不思議な気もします。
そこにあったのは、「かわいそう」と思うのは、相手を見下すことだ、という私自身の思い込みにほかなりません。私は患者さんに対して、私自身の気持ちを投影していたのでしょう。
今、かつて出会った患者さんのことを思い出すと、本当にかわいそうだったなあ、と思います。特に最近思い出すのは、50代で亡くなった患者さんのこと。私自身が50代の終わりを迎え、改めて、あの年齢で亡くなる無念を思うと、涙が出てきます。
その方は、がんの再発を繰り返しながら、仕事に戻ることだけを考えていた男性。症状が進んで具合が悪くなっても、最後まで復職を諦めず、仕事の話ばかりをしていました。
まだ20代だった私は、命に限りがあるならば、仕事、仕事ではなく、家族と一緒にのんびり過ごせばいいのに。そんなふうに思って、割り切れない気持ちでした。
しかし、今この歳になって、病気になったからといって、人間はすぐに死を意識できるものではないと気づきました。それまで生きてきたように、続きの日々を生きようとするのですよね。
それが何かもったいないように見えても、それは周囲が決めることではありません。彼は、そのように生きることを選び、おそらく家族もそれをわかって見送ったのではないでしょうか。
また、かわいそうなのは決して亡くなる人だけではありません。
若い頃働いた内科病棟では、明確な病気はないのに、身体症状を訴える患者さんもいました。亡くなる患者さんも多い病棟だっただけに、そうした患者さんに、私は冷淡だったと思います。
今私は、あの人たちはその後どう生きたのか、とても気になっています。精神科で働いてきた経験に照らすと、今なら心因反応やうつ状態といった病名がつく人たちでしょう。
実際、患者さんの多くは、家族から疎まれ、孤立していました。思うようにならない人生のなかで、身体症状が強まった人たちだったのです。
当時は余命の短い人ばかりに手厚くかかわってしまったのですが、今になると、入院してくる患者さんたちのつらさがわかり、苦しくなります。
長く看護師を続けながら歳を重ねてくると、若い頃とは感じ方が本当に変わってきます。この変化もまた、看護師を続けることの意味だと思います。
管理栄養士という職種も、きっと悩みを抱えながら患者さんに接する専門職なのではないでしょうか。(『ヘルスケア・レストラン』2022年10月号)
みやこ・あずさ●1987年、東京厚生年金看護専門学校卒業後、2009年3月まで看護師としてさまざまな診療科に勤務。13年、東京女子医科大学大学院博士後期課程修了。博士(看護学)。精神科病院の訪問看護室勤務(非常勤)を経て、同院の慢性期病棟に異動。長年、医療系雑誌などに小説やエッセイを執筆。講演活動も行う。看護師が楽しみながら仕事を続けていける環境づくりに取り組んでいる。近著に『まとめないACP 整わない現場、予測しきれない死』(医学書院)がある