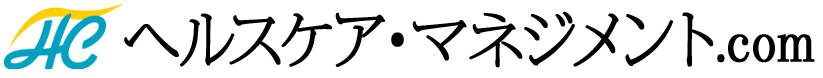栄養士が知っておくべき薬の知識
第124回
胃ろうから薬剤注入も行われる
パーキンソン病治療薬について
パーキンソン病は患者によって表れる症状が異なるため、薬による症状緩和が必須です。薬の影響で栄養管理において注意すべき点があるので、薬と併せて確認していきましょう。
パーキンソン病について
パーキンソン病(Parkinson’s Disease:PD)は、静止時振戦、筋強剛、無動・寡動、姿勢反射障害を4大徴候とする運動症状が表れます。また非運動性とされる起立性低血圧や認知障害、うつや不安、幻覚、妄想といった精神症状も表れます。栄養管理を行ううえでは、便秘が起こることも大きな問題となります。これは後述するPD治療薬の中心となるドパミンの吸収にも影響を及ぼします。
一方、これらの症状はPD患者さん一人ひとりで異なるため個別対応が求められます。このため、英国ではPD専任看護師制度を設けてその対応に当たるなど、治療とともに介護も必要となる疾患です。
PDは高齢になるほど発症率が増加するため、本邦のような超高齢社会では有病者が増加傾向にあります。PDの症状は高齢に伴う運動障害との鑑別も難しく、PDの診断に至らないケースもあります。PDは大脳のドパミン神経が脱落してドパミンという神経伝達物質が欠乏することで、さまざま症状を呈します。細胞の脱落は末梢にまで及びますが、脱落細胞ではレビー小体というシヌクレインという物質の凝集体が確認されています。この凝集を抑えるための抗体療法も行われていますが、いまだその治療法は確立されていません。もっぱら欠乏したドパミンを補充する治療が行われています。
ただし、薬として投与するドパミンは薬が効かない時間に起こるwearing off(ウェアリング オフ)※1現象ではすくみ足を生じたり、on off(オン・オフ)現象※2では急にドパミン不足の症状を起こしたりします。また不随意運動であるジスキネジア※3や幻覚・妄想といった精神症状なども生じます。
※1 治療で使う薬であるレドパの効果の持続時間が徐々に短くなり、葉が効いている時間が短くなる現象
※2 パーキンソン柄の症状が薬の効果で抑えられている状態のことをオン現象、反対に薬の効果が見られない状態をオフ現象とし、突然スイッチが入ったり切れたりするかのように出てくる現象
※3 主に口唇、舌、顔、手足など特定の筋肉に出現し、自分の意志で止めるのは難しく、止めてもすぐにまた起きてしまうことが特徴
PDにおけるドパミン補充
ドパミン自体を服用しても脳には到達しないため、ドパミンの前駆物質であるL-ドパを投与します。L-ドパは主に十二指腸から小腸の上部で吸収され、脳に達するには血液脳関門を通って移送されて、ドパミン神経細胞に取り込まれてドパミンとなります。中枢にドパミンが運ばれるとPD患者さんの運動障害の改善につながります。ただしL-ドパは食事や飲み物によって、小腸からの吸収量や吸収時間に差が出たり、脳への移送に影響を受けたりすることが知られています。
L-ドパは脳に移行する前の末梢組織の段階で、レボドパ脱炭酸酵素という酵素によって分解を受けて活性を失います。以前はこの酵素を活性化させるビタミンB6を制限したほうがよいとされましたが、現在はL-ドパに加えてこの酵素を抑えるカルビドパ(ネオドパストン配合錠L100®、メネシット®)やベンセラジド(イーシー・ドバール配合錠®、ネオドパゾール®配合錠、マドパー®配合錠)が配合されているため、その心配はいりません。
L-ドパはその吸収部位である十二指腸から小腸の上部に到達するまでの時間経過が大切です。胃から排泄される時間が長引くほど、吸収が悪くなってPDの症状改善が得られにくくなると考えられています。PDでは末梢組織でもレビー小体が発現することなどによって便秘を生じやすく、また脂肪の多い食事や牛乳の飲用によってもL-ドパの胃からの排泄時間が長くなり、吸収量低下が起こります。このため腸の蠕動を促すモサプリドや六君子湯(りっくんしとう)なども併用されます。反対にレモン水などの酸性料は、LI-ドパを早く溶解させ即効性が得られます。
またL-ドパの吸収や血液脳関門を通るといった移送時に、トリプトファンや分岐鎖アミノ酸といった中性アミノ酸との競合が生じることも考えられています。つまり、たんぱく質摂取によってドパミンの効き目が悪くなる可能性があるため、PD患者さんはたんぱく質制限が必要だといわれています。
しかし高齢者にたんぱく質制限を行えば当然、サルコペニアになります。ただでさえ運動障害が生じるPD患者さんにとって、望ましい栄養管理ではありません。できるだけ一定量のたんぱく質を摂取する一方で、薬用量や薬の服用回数などを工夫して患者さんの症状を安定させるほうが理にかなった対応方法だと考えられます。
ドパミン類似作用や分解を妨げる薬
L-ドパを使っていると精神症状の出現などといった好ましくない作用が起こりやすくなります。そこでドパミン神経を刺激する薬も開発されています。麦角系(ばっかくけい)と非麦角系があります。麦角系ではブロモクリプチン、ペルゴリドなどが開発されました。しかし、心臓弁膜症や全身性線維症が出現することなどが明らかになり、現在主に使用されるのはプラミペキソール、ロピニロール、ロチゴチン、アポモルヒネなどの非角系ドパミン作動薬です。これらの薬には長時間作用する徐放剤や貼付薬、突発的なoff症状に対してレスキュー使用目的の自己注射製剤なと多くの剤形が発売されています。
また脳内のドパミン分解を抑制するモノアミン酸化酵素B(MAOB)阻害薬のセレギリンおよびラサリンは、65歳未満で発症したPD患者さんによく使われます。このほか血中でのレボドパ代謝に働くカテコール-O-メチル基転移酵素(COMT)を阻害するエンタカポンがレボドパ製剤と併用して使われています。最近になってほかの薬で効果が十分でない無動や筋強剛に抗てんかん薬であるゾニサミドをL-ドパに加えて使用することで改善が見られた症例の報告があり、トレリーフという商品名で使われたり、off時間短縮目的にアデノシンA2A受容体拮抗薬のイストラデフィリンなどが用いられたりしています。L-ドパによって起こる振戦などのジスキネジアでは抗コリン作用をもつトリキシフェニジル、ビベリデンなども用いられます。
胃ろうから薬剤を注入するDAT
L-ドパは作用時間が短かったり、食事内容などによっても吸収量に変化を生じたりするため、十分に効果が得られない場合も多く見られます。そこで胃ろうをつくってチューブの先端を十二指腸以下に留置して、そこから直接L-ドパを持続的に投与する方法が取られており、デバイス補助療法(Device Aided Therapy:DAT)と呼ばれています。この方法は、基本的に入院して経口薬のL-ドパ必要量を厳密に決めて、その後胃ろうを造設して、そこからカセットに入った薬剤を流し込み、最終的な投与量を決定します。日中の16時間、持続的なL-ドパを投与し前述したようなL-ドパの効かない時間をつくらないようにするという方法です。胃ろうを造設して管理することから、胃ろう周囲部の皮膚の発赤やびらん、チューブの洗浄も必要になり、管理は煩雑になりますが、一定量の薬が投与できるといったメリットがあり、経口薬でどうしても症状コントロールが難しい患者さんに適応されています。
PDの患者さんの症状はとても多彩でコントロールの難しい病気です。そこでさまざまな薬や投与方法が行われています。栄養管理にも配慮するべき事項が多く、管理栄養士に意見を求められることも多いと思います。基本的に消化を含めた運動失調があるため、PDの症状管理を安定されるために炭水化物に偏った栄養管理が実施されがちです。しかし他職種と連携して、個々の患者さんの症状や全身状態を把握して適切な栄養管理をめざしていただけたらと思います。(『ヘルスケア・レストラン』2021年12月号)
はやし・ひろゆき●1985年、日本大学理工学部薬学科卒業。88年、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院勤務。2002年から同院NST事務局を務める。11年4月から日本大学薬学部薬物治療学研究室教授