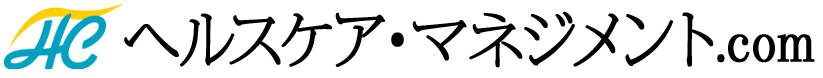お世話するココロ
第123回
KENZOの思い出
10月4日、パリ在住のファッションデザイナー・高田賢三氏が亡くなりました。享年81歳。新型コロナウイルス感染症による合併症が原因と報じられています。彼の美しい服は、私の人生にも大きな影響を与えてくれました。
高田賢三という人
20代後半から40代にかけて、私はKENZOの服ばかり着ていました。KENZOは高田賢三が設立したブランド。1999年に高田賢三が退き、ほかのデザイナーに変わりました。それでも国内に店舗があった2012年頃までは、お気に入りのブランドでした。
私がここまでKENZOの服に入れあげたのは、なにより華やかな色彩と柄の、エスニックな作風が好きだったからです。加えて、高田賢三という人にも魅力を感じました。
高田賢三は、戦後男性にも門戸を開いた文化服装学院を卒業した最初の男性の1人です。65年、無名のデザイナーとして渡仏した資金は、当時住んでいたアパートの建て替えに伴い受け取った、25万円の立ち退き料。半年で帰国する予定だったと聞きます。
ところが、勇気を振り絞って有名ブティックに持ち込んだデザイン画が評価され、パリでの生活が軌道に乗りました。以後、デザイナーとしても仕事を得、70年、ついに自らのブティック「ジャングル・ジャップ」をパリに出店したのです。
96年12月の1カ月間日本経済新聞に連載した『私の履歴書』で、彼は77年の人生を振り返り、こう書いています。「1970年代がデザイナーとしては最も輝かしい。自分が好きな服だけを作っていた」。
姫路で芸者さんたちが出入りする待合を営む家に生まれた彼は、着物に親しみ、華やかな色使いに長けていました。さらに、パリへ向かう船旅で寄港した街でさまざまな民族衣装に触れた体験が、彼の作風に大きく影響したと、彼自身が語っています。
70年代の服は、図版や録画などで知るだけですが、斬新で華やかで魅力的で……。当時のパリで熱狂的に迎えられたというのも、よくわかります。
KENZOブランド設立後は、世界にブティックを出すほか、小物や香水まで、さまざまな分野に進出しました。しかし、93年に会社をルイ・ヴィトンのグループに売却。自身は雇われデザイナーとして、KENZOの服をつくり続けます。
長くKENZOの服を愛してきた友人によれば、やはりこの年を境に、KENZOは好きな服をつくれなくなったように見えるそうです。確かに、流行に合わせた服をつくるようになりました。経営と創作を両立させるのは、大変なことなのでしょう。
晩年は、思うような創作活動ができなかったようにも見えます。それでも、高田賢三がファッション界に残したものは大きかったと思います。
KENZOの時代
私がKENZOの服を着るようになったきっかけは、ヘトヘトになって帰宅する夜勤の朝、家に帰る途中で目にしたウィンドウの華やかな服でした。確か89年の春頃のこと。当時、今も暮らす吉祥寺には伊勢丹デパートがあり、その1階にKENZOショップが入っていたのです。
看護師になって3年目に入る頃、私は悩みが深まっていました。ちょうどバブルの時代、患者さんを巡って財産問題が持ち込まれるかと思えば、金にものをいわせる患者さんもいるなど、嫌というほど、人間の裏側を垣間見たのです。
その朝も、いろいろあって、泣きたいような気持ちで帰宅していました。細かいことは忘れましたが、患者さんからものすごく理不尽なあたられ方をして、暗い気持ちになっていたと記憶しています。
少し街中をぶらついて帰ろうと回り道をして、そして、KENZOショップのウィンドウに目が行ったのでした。今までにも見ていたはずの景色。でもこの時は、飾られた服の鮮やかさが目に染み、励まされる気持ちになりました。
それまで私はエスニックな安い服ばかり着ていたので、服に高いお金を払う人の気が知れませんでした。それどころか、バブル時代特有のブランド信仰が腹立たしく、無視を決め込んでいたほど。
にもかかわらず、KENZOの服に魅入られてしまったのです。
ちょうどこの頃から看護師として働きながら始めた著述の仕事も増え、給料以外の収入にも恵まれました。さまざまな収入の多くをつぎ込んで服を買い、人前に出る時はKENZOの服。そんな時代に入ったのです。
うれしいことに、KENZOショップで働くハウスマヌカンさんは、多くがKENZOのファンでした。パリから時々帰国する高田賢三と会った人もいて、KENZOという会社のファミリー的な雰囲気も、魅力だったのです。
KENZOを買わなくなってもう10年ほどになります。お世話になったハウスマヌカンさんたちも、それぞれ別の道に進みました。それでも、何人かの方とは、今も細々ながら交流があり、これもKENZOの服が持つ力なのでしょう。
服と人生
悲しいことに、たくさんあった服も、長い年月の間には色あせ、痛み、かなりの数を処分しました。特に、高田賢三がデザインしていた99年までの服は、残りわずか。
多くは捨て、きれいなものは人にあげたりして、手元を離れていきました。
それでも最初に買った赤い小花のツーピースは絶対に手放しません。私がショーウィンドウで目に留めた鮮やかな服。決意して買ったのに気後れして、実はあまり着ていないのです。
高田賢三の訃報を知り、この服を広げてみました。じ~っと見ていると、20代半ば、この服を買った当時のことをいろいろ思い出します。やっぱり若かった。今なら「しょうがない」と思えることが思えず、苦しかったんですよね。
たとえば、糖尿病の患者さんが隠れて大福を食べているのを見つけた時のこと。夕食前の血糖値を図ったらものすごく高くて、「何か召し上がりましたか?」と聞くと、「何も……」の返事でした。
ところが、顔をじっと見ると、口元に白い粉がついています。そしてゴミ箱を見ると、大福の空き袋……。激怒した私は、厳しく注意しました。
「大福なんか召し上がるから、血糖が上がるんですよ! 合併症のお話をしたばかりじゃありませんか。きちんと守ってください」
当時は、注意を守らないで状態が悪くなる患者さんを許せない気持ちが強く、この時も、80代の男性に、強く怒っていました。
今ならどうかといえば、多分、笑ってしまうでしょう。だって、口元に大福の粉をつけて、「何も……」なんて言っちゃう。まるでギャグですよ。
人間、食べたいものを我慢するのはとっても大変なんですよね。そんな身体になった患者さんは、やっぱり気の毒だと思います。
そう思えば、見え見えの嘘をついたその人への怒りも、大して湧かないというか。「まったくしょうがないなあ」と笑いながら、「でもこの血糖値はまずいですよ」とたしなめる。今ならそんなかかわりをするでしょう。
人を許すことが難しかった若さと共に着始めたKENZOの服は、その後も私が生きた時間を彩ってくれました。一生懸命働いて、一生懸命服を買った日々。高田賢三の死は、改めてそんな日々があったことを、私に思い出させてくれました。
そんな服に巡り会えたことに感謝しつつ。ご冥福をお祈りしています。(『ヘルスケア・レストラン』2020年12月号)
みやこ・あずさ●1987年、東京厚生年金看護専門学校卒業後、2009年3月まで看護師としてさまざまな診療科に勤務。13年、東京女子医科大学大学院博士後期課程修了。博士(看護学)。現在は精神科病院の訪問看護室に勤務(非常勤)。長年、医療系雑誌などに小説やエッセイを執筆。講演活動も行う。看護師が楽しみながら仕事を続けていける環境づくりに取り組んでいる。近著に「宮子式シンプル思考 主任看護師の役割・判断・行動力」(日総研出版)がある